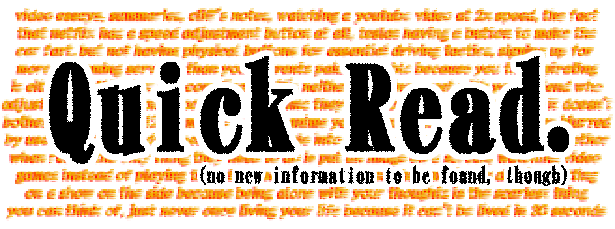「カミカゼ特攻隊で、まじめに人殺し労働にはげんだ親父が、肉体的におとろえはじめて「速度」を忌み出す頃、ぼくたちの週刊誌のグラビアにはスポーツカーや盗塁王、そしてジェット機「よど号」など、速いものの記事が氾濫する。速度は、ぼくたちのなかでは次第に存在論を形成しはじめるが、親父たちの肉体ではついて来るのがムリなのだ。速度といえば、サラブレッドのことを思い出し、「ホースニュース」紙をわしづかみに競馬場へといそぐ親父よ。レースにおける速度は比喩の世界のものだが、ぼくたちにとって速度は実存なのだということを、あなたにはどうやって説明したらいいのだろう。
何しろ、速度は僕達の世代の「もう一つの祖国」であり、とても住みやすいものだ。Jブルボンは旧世代に向かって「ぼくらにとって人生は英雄的な事業ではなくなった」と宣言しているが、この心情は時速
500キロで、歴史を乗り捨てる意気地から生まれたものだということが、わかるだろうか、親父よ。」
寺山修司、「書を捨てよ、町へ出よう」
1967年に真実だったことは、今もほぼ変わらず真実である。
人間とは速いもの(早いもの)に憧れ続ける生き物だ。できる限り速く、若くして死ぬことを追い求める。速く走る車、速いインターネット、ファストファッション、ファストフード、速くダウンロードできるインターネット、高フレームレート、新幹線、プライベートジェット、24時間休まない株式市場、飛び級、年上の同僚より早く昇進すること、30歳までに10,000万の収入を得ること、短期間で大量の作品を生み出すこと、彼氏彼女を次々と乗り換えること、など、これ以外にも「速さ・早さ」を、私たちは求め続けている。
寺山修司も「今」という瞬間に取り憑かれた芸術家だった。きっとそれは僕が今挙げたどの「速さ」よりも、さらに速く消え去るものであることを意味するだろう。
彼が主催した劇は街中で上演されたし、彼の映画は途中で映画であることを放棄しながら、観客に向かって「お前は人生を生きていない」と詰め寄ってくる。これは彼がベールに覆われた日常を切り裂き、動かしているエンジンを大破することに執着していた証拠だ。
「速く生きる」ということが彼の活動であり、矛盾であり、一種の反抗でもあった。それは、彼の前の世代が頑なに守り続けようとした「現状を維持する」ということに対立することだった。それは彼の活動すべてに現れていた。寺山修司にとって、それは抗議の手段だったのだ。
しかし、寺山修司が夢中になった「速度」というロマンチックな概念は、今ではすっかり商品化され、当たり前になってしまった。
世界は日を追うごとに速く回転し、常に目を覚ました状態だ。寺山修司が1960年代にかすかに感じ始めていた予感を現実のものとして、私たちは生きている。「すべてが速くなりすぎた」なんて月並みなことを言うつもりはない。
そんな話は、きっとあなたも友達とよく言い合ってることだろう。「メモリーホール」、つまり何かが大きな話題になっても、次のトレンドやスキャンダルが出てくるとすぐに忘れ去られ、まるで最初から存在しなかったかのようになってしまう。「ドゥームスクロール」、災害、戦争、経済不安、犯罪、炎上などの悪いニュースを次々と見てしまい、気分が沈むのにやめられない状態、こういったことが日常になりつつある世界。
瞬きをしている間に、すべて消えてしまう。
タイムラインに流れなかった出来事は、存在しなかったことになる。
でも、去年、僕がヨーロッパを旅していた時、どこの国でもいいから使い捨てカメラを手に入れたくて探し回っていた。
プラハのどこかで、20世紀の大半をカメラ店で過ごしてきたであろう老人が教えてくれた。
「中国の工場が需要に追いついていないんだ。もう1ヶ月以上、1台も入ってきてないよ」
……マジか。
カフカ博物館をかわいくアナログな方法で撮ろうと思ったのに、どうすりゃいいの?
けど昔はアナログが最新技術であったのでみんな使ってたが、今頃は完全に雰囲気作りのためなものだ。上記のものを買う人はみんな自分の記憶をその隙間的なアナログとデジタルの間にあるテクノロジーで思い出したいけど、写真の画質やカメラがその雰囲気を出すものじゃなく、取った人の目線だった。
使い捨てカメラ、ポラロイド、レコード、21世紀に発売されたアルバムがカセットで発売されること、こういったアナログが今は流行りになりつつある。
ただ、これは純粋に美しいかそうでないか、に基づいていると思う。アナログとデジタルの狭間だった時代特有の、言葉では言い表せないような質感で自分の思い出を彩りたいだけであり、当時の写真が美しく見えるのは技術的なことではなく、それを撮った人々の手によるものだということを理解している人はどれくらいいるのだろうか。
食べ物も同じだ。朝のコーヒーを挽くスピードをゼロにする方法を語るReddit(海外の2chのもっとカジュアルなやつ)の投稿が山ほどあり、料理の創造性を完全に奪うかのように材料とレシピを一緒に送ってくるサービスもある。コロナの初期にみんながパンを焼いていたのを覚えているだろうか? うちの父ですら挑戦していた。
21世紀は、新たに「ゆっくりすることが美学」と言われる時代になったようだ。誰もが「田舎に移住して自給自足の生活を送る」とか「山奥に籠りたい」とか「悟りを開きたい」と言っていた。ジブリの切り取り動画を拡散している人たちは、こういう人たちとさほど変わらない。
ジブリのキャラが食事をしているところや、勉強しているところ、美しい草原や風景。そういったものの寄せ集めは宮崎駿の描く世界の足元にも及ばないし、見ているこちらに何の感動も与えない。これは、流行の新作ドラマに関するコメント動画を見るたびに、さらにそれをバカにする動画が出てくる現象と似ている。そして、そのコメント欄は炎上するものの、どの人間も、実際にそのドラマを観たことがない。今を生きる人々は、観たことのない映画やドラマについて意見を言ったり、読んだことのない本について語り合おうとしたり、触れたことのないアーティストを評価するようになってしまった。
僕たちは速く生きたい。でもそれと同時に、ゆっくりと生きる満足感も味わいたい。ウサギでありながらカメでありたい。草原に寝転ぶだけで満ち足りた世界を想像することはできたとしても、結局のところ、それはあくまで想像の域を出ない。
この手の話題は、(ギー・ドゥボール的な意味での)スペクタクルや(ジャン・ボードリヤール的な意味での)ハイパーリアリティ、そして(メタルギアソリッド2的な意味での)ポストモダニズムへと、なし崩し的に辿り着いてしまう可能性がある。でも、そういう方向に話を進めたくない。なぜなら、ダナ・ハラウェイが書いたように、ポストモダニズムとは、「ブルジョワの父親を持つ息子たちが、彼らを育ててくれた手に反抗して殴りかかること」以上のものではないかもしれないからだ。こういう話をすると、月並みな言葉に着地しがちで、最終的には「ほらな? あのフランスのやつらは正しかったんだよ!」という話にしかならない。
僕が言いたいのは、みんなが望んでいる「ゆっくりとした生き方」をするのに、バカみたいな金額を出して「エシカル」なコーヒー豆を買ったり、富士フイルムに高額を支払って訳もわからずポラロイド写真を撮ったりする必要はない、ということだ。(しかも、その半分は露光ダイヤルの設定を間違えて台無しにしてしまう。だって、アナログ写真の仕組みなんて誰も分かっていないから。大丈夫、かくいう僕も分かってないから)
最近、友達とした会話について話を広げたい。
「何かをしながら流し見してる番組ってあるよな?」
「は? いや、それだけを観るよ。特にそれを初めて観る時はなおさらね」
「どういう意味?」
「つまり、部屋の電気を消して、スマホもしまって、トイレに行く以外、観てる時は画面しか見ないってこと」
「でもナルトとかは? 他のことしながら観てもいいよな?」
「ナルトでも、エヴァンゲリオンでも、何だっていいけど、もし『ながら見』できるくらいどうでもいい作品なら、そもそも観る必要ないってことだろ。そんなに興味がないなら、最初から観ない方がいい」
その時、うわ、僕ってめんどくさい奴だなって思った。でもまあ、たまにはちょっとくらい面倒くさい奴になったっていいじゃないか。でもそれと同時に、なぜ僕がこんな考えを持つのか、そして、なぜ芸術作品に全身全霊で向き合うべきだという意見があまり聞こえてこないのかを、改めて考えた。それがたとえ「ナルト」であったとしても、(いやもちろん、「ナルト」であるべきだけど)なぜそうなのか、改めて考えたい。
「ブレイキング・バッド」というドラマを見た人がどれくらいいるかわからないが、そこに出てくる
登場人物のジェシーが「自分の理想の人生」について語る場面に触れたい。あのシーンで彼が望んでいるのは、子供の頃に作ったようなシンプルな木箱をもう一度作ること、だったそれだった。
最近、僕も彼と似たようなことをした。昔遊べなかった日本のゲームをプレイしたくて、スケルトンのゲームボーイカラーを買った。でも、実際に届いたものを見たら、ボロボロで黄ばんでいて、到底「クリア」とは言い難い。そして画面も驚くほど暗い。僕はこれをバックライトなしでどうやって遊んでたんだろうか?
そこでアリエクスプレスでバックライト付きのスクリーンを注文した。1週間後、それが届いたので、その日の午後全てを費やしてゲームボーイを分解した。肺に障害が残るんじゃないかと思うくらい強い洗浄液を作りながら、改造作業に取りかかった。こういう作業は得意じゃないけど、心のどこかで「僕の家系は代々エンジニアだから、絶対できる」と根拠のない自信を持っていた。(もちろん、お察しのとおり、見事に失敗したけど)
日が暮れる頃、リボンケーブルを何度も調整して、ようやく組み直したと思ったら、画面がほんのわずかにズレている。わずか数ミリとはいえ、こういうのは一度気になりだすとダメなたちだ。もう一度やり直し。いや、大丈夫、全然気にしてない。むしろ、こういうのが楽しいんだ。最後にネジを締めようとした瞬間、暗い緑色のモダンなカーペット(小さい物体を見つけるには最悪)の上に小さな黒いネジを全部床にぶちまけてしまった。すでに夜になっていて、ネジは全然見えない。でも、踏めばしっかり感じる。
それでも、なんとか組み立て直して、カセットをセットした。昔、いとこからもらった「ポケットモンスター ダイヤモンド」が、実は海賊版の「テレファング」だったことを思い出しながら選んだのは「携帯電獣テレファング」。ゲームボーイの電源を入れる。スピーカーから音がかすかに入ってくる。画面の向こうにゲームの世界が生まれてくる。
そうこうするうちに、僕は夜が明けるまでプレイを続けた。ただゲームが面白かっただけじゃない。それ以上に、「汗水を垂らしながら改造した機械で、自分のためだけに遊ぶ」という行為が、この瞬間最も完全で、圧倒的な満足感をもたらした。その瞬間、なんというか、心がすごく澄んでいた気がした。
道具を捨て、外へ出よう。コーヒーを淹れる道具なんて捨ててしまえ。近所の古本屋に足を運び、200ページの小説を手に取り、最後のページまで読むか、少なくとも寝そうになるまで読み続けろ。何ヶ月も後回しにしていた3時間の映画を再生し、途中で席を立つな、スマホを見るな、寝るな。ゲームをプレイし、攻略サイトを使わず、エンディングまでやり遂げろ。周りが明るくなってきたら、目の回るような速さで進む世界に戻らなければならない。でも君はすでにゆっくりとした時間を見つける術は身につけているはずだ。なぜならどこまで突き詰めても、人や物事に対して「ちゃんとする」以外に対処する方法はないからだ。
芸術は人類がまだ洞窟にいた時代から存在している。それに比べれば、資本主義なんて最近のものだ。しかし、僕たちは芸術を単なる消費物と錯覚して、本来の姿である「人と人との対話」として扱わなくなってしまった。芸術に敬意を払わないことは、自分自身を悪に染めるような行為だ。どんな映画を観ても、どんなゲームをやっても、「それが楽しめるかどうか」だけで評価し、それ以外は金を払う価値がないと切り捨てたりしていないだろうか?僕はこの考えが完全に間違っているとは言わないが、芸術に対する接し方を少しだけ変えて欲しい。もし、誰かが「君が面白いかどうか」で君との関係を判断していたら、どう思う?誰かに本気で思いを打ち明けている時に、その相手がスマホをいじってたら、どう感じる?
すべては繋がっている。もし君が意識を変えれば、友達との何気ない会話がこれまで以上に面白く感じられるかもしれないし、ライブ会場で隣にいるおじさんが語る昔話に、思わず耳を傾けるかもしれない。妹が語るテイラー・スウィフトのアルバムについての考察が、妙に納得できるようになるかもしれない。そして何より、自分の声をよりはっきりと聞くことができるようになるだろう。
「僕はちゃんと何かを成し遂げているのだろうか?」という頭の片隅にこびりついた不安を感じることもある。でもその答えは、あれこれ手を出してやってみることではなくて、目の前のことに集中することにある。「ながら見」はただの気休めにすぎない。でも、これは君を馬鹿にして言っているわけじゃない。スマホを見ながら映画を観ると、映画もスマホもただの雑音になってしまうし、「そもそもなんで映画を観ようと思ったんだっけ?」と思ってしまう。YouTubeでショート動画を延々と見たあとに、心から「観てよかった」と思ったことがあるだろうか?その選択に対して、誇りを感じたことは?なんとか脳を刺激しながら、「僕もいつか死ぬ」という現実を誤魔化しているだけかもしれない。しかも、その行為をすると死に際にたどり着くと倍に辛く感じるだけだ。
僕たちはゆっくり生きる動物だ。我慢できないほどのゆっくりとした速度で生きながらも、そこに魅力を感じている。まるで、ゆっくり生きればゴールにたどり着かずに済むと思ってるかのようだ。だからこそ、速さや刺激に惹かれるんだ。でも、何事も「ほどほど」が大事だってことを忘れないで欲しい。誰もがこのことを理解しているからこそ、「あらすじを読んだだけで小説を読んだ気になるな」と言われると、恥ずかしくて気まずい気持ちになる。そして、その恥ずかしさや後ろめたさから抜け出すために必要なことは、本を読むことだ。なぜなら「努力が必要だから」だ。でも、それは君が思うほどそんなに大した努力じゃないから構えないでいい。むしろ、やってみれば拍子抜けするくらい簡単で、その分だけ確実に満たされた気分になるはずだ。
16歳の時の僕は、同時に7本のRPGゲームをやっていた。どれもクリアできないことに絶望し、どうしたらいいのか分からなかった。当時の僕にとって、PS2の「真・女神転生」シリーズをすべて並行して遊ぶ誘惑に勝てるわけがなかった。でも、高校生で50時間以上かかるゲームを何本も同時に進めるなんて、どう考えても無理に決まってる。結局、ゲームを楽しむことよりも「何を遊ぶべきか」という悩みが上回ってしまい、全部やめた。セーブデータも消した。
それからは、短いゲームをクリアすることで「ゲームを最後までやり遂げる感覚」を取り戻そうとした。初めて「メタルギアソリッド」をプレイした。そこからそのシリーズ作品を2、3、4と続けていき、気づけば自然と「メガテン3」のマタドール戦の前に戻っていた。それは、至極当然の流れのように思えた。7本のゲームを同時に進めること頭を悩ませるより、ずっと簡単で、ずっと速い時間でそこにたどり着くことができた。
つまり、16歳の僕にできたんだから、君にもできるはずだ。
翻訳:神原桃子
投稿日:2024年1月14日
日本語版:2025年3月16日
監修:アマスヤ・デニズ